対象魚:サヨリ・カマスなど
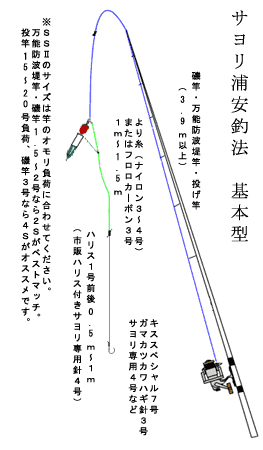
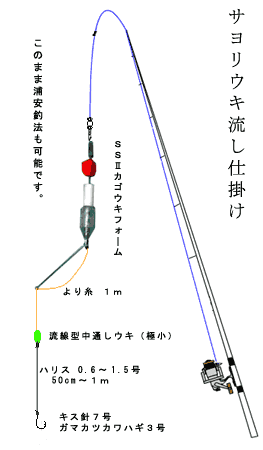
カメジャコやボケジャコ餌の場合、尻尾から二節目をたたんでチョン掛け。必ず餌の中心にハリを刺すこと。イソメ餌の場合はチモト上2〜3cmほどまでコキ上げ、タラシは3〜5cm。針先は出して、針の軸に対して餌が真っ直ぐになるように付けること。餌の中心からずれていたり、曲がっているとプロペラのように回転して、ハリスのちぢれや仕掛け絡みの原因になる。誘いを掛けたときの動きも不自然で食いが悪くなってしまう。
投入は竿の弾力を活かしてソフトに。
フルキャストすると餌の弱りが早いし、投入時にちぎれてしまう事もある。
【カメジャコのチョン掛け】
誘いの掛け方
オモリが着水したら竿を起こして、1mほど仕掛けを引いて仕掛け絡みを防ぐ。
仕掛けが着底したらゆっくり竿を立てて道糸を張り、竿先で海底の凹凸を感じ取りながら誘いを掛け続ける。竿の弾力でオモリが海底をズズッと引きずったら5秒ほど誘いを止めてアタリを待つ。アタリがなければ再びズズッと誘いを掛ける。
根掛かりの外し方
誘いを掛けている最中に、オモリが障害物に当たる「ガリガリ」とか「コンッ!」という感触を感じたら、誘いを掛けるのをやめて道糸を少し緩め、竿を頭上に高く差し上げて竿先を前後にピュンピュンと振ってみる。多くの場合はオモリが障害物に当たっているだけの状態なので、ほとんどの根掛かりはこれで外れるはずだ。どうしても外れない場合は竿をグイグイとあおらず、道糸と竿が一直線になるように竿を倒し、リールのスプールを押さえて後に下がる。もしくは道糸をタオルなどでつかんで引っ張って仕掛けを切る。根掛かりした場所までの距離が近いと、ハリスが切れてオモリが弾丸の様に飛んでくることがある。周囲の釣り人にも声を掛けて注意を促し、自分も必ず半身に構えておくこと。3号のナツメ型中通しオモリの直径はおよそ8mm。ベレッタ、ルガー、ワルサーなどの拳銃弾(9mm弾)と同じくらいの鉛玉が飛んでくるのだから、非常に危険だということを覚えておいて欲しい。
アタリの取り方とアワセのタイミング
竿先にゴッゴッ、グングンとアタリが出たら、糸フケが出ない程度に竿先を送り込む(竿を前に倒す)。グーッと竿先を引き込んだら、竿を身体に引きつけるようにグイッと大きくアワセを入れる。竿先だけでビシッとしゃくるアワセは、20m以上の距離で魚が食った場合、道糸の伸びや竿の弾力に吸収されてアワセが効かないので、必ず竿を身体に引きつけるように大きく竿を起こしてアワセを入れること。
ヤリトリのコツ
針掛かりした魚は異変を察知して遁走を始める。魚が沖に走ったときは無理に寄せようとしないで、できるだけ竿と道糸の角度を直角に保ち、竿の弾力とリールのドラグで引きをいなす。リールのドラグは厳密には釣行前にバネ秤を使って、ハリス強度の限界よりもやや緩めに設定するが、感覚的には手でゆっくりグーッと道糸を引いてみて、ジリジリ……と滑り出す程度に設定しておく。ガチガチに締め込んだままだと、魚の急な突っ込みに対処できない。
クロダイやマゴチは海底に沿うように走り、スズキは海面にジャンプ(エラ洗い)する。
クロダイやマゴチの場合は竿を立て、魚を浮かせるように誘導して根掛かりを防ぐ。
スズキの場合は竿を横に寝かせて低く構え、エラ洗いによる針ハズレやハリス切れを防ぐ。
フワッとした前アタリからグ〜ンと走り出し、海底に張り付いたように動かなくなるのは外道のエイ。無理に竿を起こして引き寄せようとすると竿が折れてしまう。竿と道糸の角度を直角に保ち、ユックリと自分自身が後退し、道糸を巻き取りながら前に進む。この動作を繰り返して引き寄せる。
取り込みのコツ
タモを入れるのは魚を足元まで引き寄せて海面から顔を出させ、空気を吸わせて抵抗が収まってから。魚に元気が残っている間にタモを海面に近づけると、タモの影におびえて再び必死の抵抗を始めてしまう。あわてず、あせらず、充分に空気を吸わせてから魚の頭の方からタモを近づけ、タモ枠に頭が入ったら竿先を下げて道糸を緩めてやる。これで魚は自分からタモの中に入ってくる。タモに魚が入ったらすくい上げるのではなく、タモの柄を収納しながら真っ直ぐに引き上げること。柄を伸ばしたまま持ち上げると、タモ枠が壊れたり柄が折れてしまう。
取り込み後の注意
スズキのエラブタはカミソリの様に鋭い。うっかりつかんだりすると手指を切ってしまう。
マゴチはエラブタに鋭いトゲがあり、歯も鋭いのでたたんだタオルなどでつかむこと。
クロダイは貝やカニをかみ砕く強靱なアゴをしているので、口の中に指を入れないこと。
エイは尾びれに2〜3ヶ所の毒トゲを持っている。刺されないように注意。